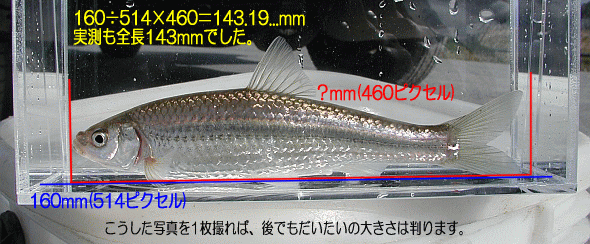|
|
|
|
魚を横から撮ることで、ある程度は種類が判る写真になりますが、
それは横に同定ポイントがある種類だけです。
類似する種類との識別点が、背側や腹側にある場合は、
どうしても上や下から撮る必要があります。
また、ドジョウ類の髭の本数は、正面からでないと数え難いなど、
種類の特徴を最大限に現すために、横からだけではなく、
上・下・正面からも撮るとより良いです。
|
●横から撮る

横からは魚撮影の基本です。頭左向き(左体側部)だけ撮れば、多くの種類で問題ありません。
横から撮影したつもりが、やや斜め上から撮ってしまうことがあります。
これは魚の高さが不正確になり、体高比などの同定に必要な情報が使えなくなります。
斜め上からの撮るのも良いですが、1枚は横(真横)からも撮ることをおすすめします。
また、シマドジョウ属は左右の模様が非対称なことがあり、写真を編集で左右反転することは良くありません。
頭右向き(右体側部)も撮ります。
|
●上から撮る

横の写真だけでは胸鰭の大きさや、体の厚みなどが分かり難く、上からの写真がそれを補います。
横からと合わせて上からの写真があれば、魚を立体的に捉えることが出来ます。
アクリルケースへ入れて上から撮ると、取り囲むアクリル板が映り込んだりして、
簡単に良い写真は撮れません。そこで発砲スチロールトレイやプラスチックバットのような、
水深の浅いモノクロの入れ物があると便利です。
タナゴ類など体幅の薄い魚は、こうした入れ物に水を少しだけ入れ、魚を横に倒して撮ることも出来ます。
|
●下から撮る

魚を引っくり返すと、すぐ元へ戻ってしまい、腹面の写真は撮れません。
そこでタオルで包み込むようにすると、写真を撮る程度の時間であれば、
引っくり返ったまま止まっています。アクリルケースを持ち上げて、
下から撮影することも出来ますが、アクリルケースの底は傷付きやすい場所で、
新しいもの以外の利用は難しいです。また、撮影し難い体勢になるのと、
光は下から差し込まないため、暗いピントのずれた写真になりがちです。
タオルに乗せる方をおすすめします。
|
●正面から撮る

通常は横・上・下の3つを撮れば、同定に問題ないことが大半で、正面から撮る必要はありません。
しかし、ヨシノボリ属のように胸鰭軟条数が同定の決め手になる場合があり、
正面から撮るとそれがはっきり数えられるため、撮っておくのも良いでしょう。
|
|
|
|
|
魚の大きさがわかるように、定規や方眼紙を背景に貼り付けた撮影用ケースを見かけます。
魚との遠近によって、実測とは数cmも違ったり、全長15cm以下の小魚を撮るのに、然して大きさが必要とは思えません。
目安としての大きさであれば、撮影用ケース全体の写真を1枚撮れば済みます。
アクリルケース(N-1600F)の幅は160mmと決まっているため、それだけでスケールの役割を果たします。
写真編集ソフトウェアを使った魚の全長の計算方法は、まず、真横に撮影した魚の腹側真中へ、底板に沿った線を引き、距離をピクセルで出します(青線)。
魚体の前端と、尾鰭を中央に寄せた後端(位置は想像)に垂直線を引き、その間の距離をピクセルで出します(赤線)。
「アクリルケース幅mm÷アクリルケース幅ピクセル×魚全長ピクセル=魚全長mm」で求められます。
計算が面倒であればアクリルケース幅から想像するだけでも、ある程度の大きさはわかると思いますし、
魚の大きさが本当に必要であれば実測することです。
|
|
|
|
|
私のように下手な写真もソフトウェアがあれば、ちょっとした作業で見違えるように変わります。
写真編集ソフトウェアは多くありますが、
私は主にIrfanViewを使っています。
どのソフトが良いというよりは、元の写真がピンボケしていると、
極端な改善は望めないため、まずはピントの合った写真を撮ることが大事です。
|
●切り取り

ピントが合っている綺麗な写真でも、
尾鰭が切れているだけで、同定が困難になることがあります。
尾鰭の上葉と下葉のどちらが長いか、尾鰭の後端が尖っているか丸いか、
尾鰭の後端にどんな模様があるかなど、魚は全身が撮れている必要があります。
|
●明るさ、色調、シャープの調整

暗い写真は明るさや色調を調整します。それだけで随分と違った感じになります。
また、ピンボケ画像はシャープをかけると、ピントが合ったように見えます。
これらは多くの写真編集ソフトウェアで簡単に調整できます。
撮影時に肉眼で見た魚の色合いに近付けるのが基本です。
|
|
| ここだけは抑えておこう |

|
| デジカメ | ノーマルのマクロモード。 |
| 水道水 | 綺麗に撮れる。汽水魚は不可。 |
| 光 | 魚の上から強い光を当てる。 |
| アクリルケース | カラー背景や定規は不要。 |
| 撮る位置 | 横と上の2枚は撮影する。 |
| 魚体 | 髭先から尾鰭まで全体を撮る。 |
| 写真 | 暗い写真は明るくしてシャープ。 |
|
|
魚の写真を確り撮ることは、その魚がその場所に居た証拠にもなります。
しばしば適当に魚を撮っても、同定できると思われていますが、
実際には軟条数や側線鱗数など細部を見る必要があり、
そうした所がわからないと「たぶんこの種類でしょうね」とするしかありません。
折角なのでアクリルケースの上から強い光を当て、
魚の横からピントの合った写真を撮りませんか。
インターネットに採集魚の写真を載せている方の中には、
アクリルケースの後ろ側に景色が写り込み、場所が分かるような写真も見かけます。
インターネットで生息地を探す人は多く、
その写真が原因で乱獲などの問題になった場合、取り返しが付かないため、気を付けたいところです。
最後に撮影へご協力下った方々に心から感謝致します。
|